| |
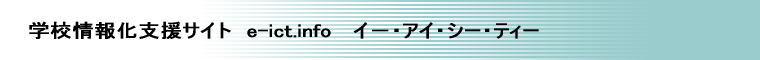

|
学校で扱う個人情報は、質と量のいずれにおいてもけた外れに大きいものです。 ざっと上げて見ましょう。
生徒個々の基本情報(住所・性別・氏名・生年月日・電話番号)はもとより、高校生なら入学試験での中学内申点や学力検査の点数、在学中のすべての成績、取得した資格、病歴や健康状態、出席状況、身長体重などの体位、心電図や血液検査の結果、運動能力、交友関係、家族の氏名、家族状況、通学経路、部活動、趣味特技、癖、顔写真、授業料納入状況、 最近はどこの学校でも、これらの情報が各部署(分掌や学年、担任)によって電子化され、必要に応じて利用されていると思います。 こういった情報の扱いについては学校ごとの規則や教育委員会の指導によって厳しく管理されているはずですが、ときたま店舗等の駐車場にとめた車からPC本体や記録媒体 が盗難される事件が報道されるのは残念なことです。 一方で、学校で扱う個人電子情報の信憑性はいかがでしょうか。意図的な(内申書等の)改ざん事件は大きく取り上げられたものの、データの入力時や加工時のミスがマスコミによって取り上げられたという記憶はわずかです。私の30年間の教師生活においても、ミスはあったとしても何らかの経緯を経て必ず 入力後程なく修正されて来たものです。 入力のミスは、学校現場では比較的発生しにくいと思います。 その理由はおおよそ以下の各点によるものと考えられます。
ところで、社会保険庁による年金データの電子化作業においてはどのような注意がなされていたのでしょうか。 上記①~④との比較を試みます。 ①いわゆる「申請主義」ということで、被保険者が求めなくては開示されない。 ②紙媒体(納入原本)は入力終了後に当時の社会保険庁によって破棄された。 ③人事異動時の情報の引き継ぎのありかたについては不明。 ④上記④ほど慎重に入力を行ったということはなさそう。(具体的な電子化作業の方法は報 「いまさら感」がありますがマーフィーの法則です... ・失敗する可能性のあるものは、失敗する。 ・何でも長期間持っていると、捨てやすくなる。捨てるとすぐに必要になる。 ・コンピュータは信頼できないが、人間はもっと信頼できない。 ◆お問合せ・ご意見(e-mail) dnspb294@icloud.com |
||
|
本サイトについて |
シェアウェアソフト紹介 | |
|
|
マークシート画像採点・解析プログラム [ダウンロード (Vector)] 詳しくはこちらをクリック
|
|
Copyright (C) 2007 e-ict.info . All Rights Reserved.
