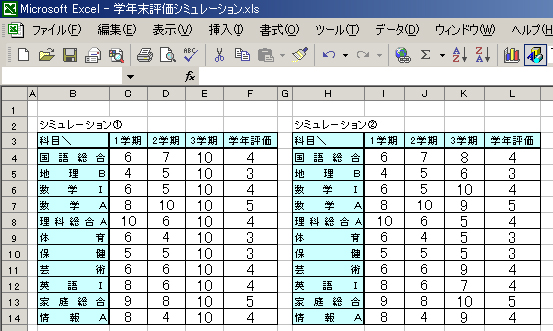| |
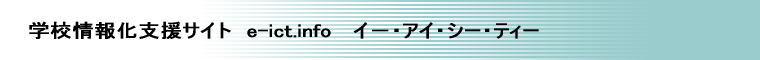

|
7.問題解決も表計算ソフトで
1・2学期の成績が出て、残る3ヶ月で学年評価が決まるわけですが、そこで考えたのが「学年評価向上計画立案」をテーマにした授業。次のように問題解決の手順に則って考えさせます。→配布資料(Word)
(授業のあらまし)
③情報の分析・加工:Aさんの場合を例にしてシミュレーションを実行
【結論の例】下図のどちらでも学年評価はまったく同じになる。(右は「最低目標点」と位置付けられる。)
|
|
|
本サイトについて |
シェアウェアソフト紹介 |
|
|
マークシート画像採点・解析プログラム [ダウンロード (Vector)] 詳しくはこちらをクリック
|
Copyright (C) 2007 e-ict.info . All Rights Reserved.